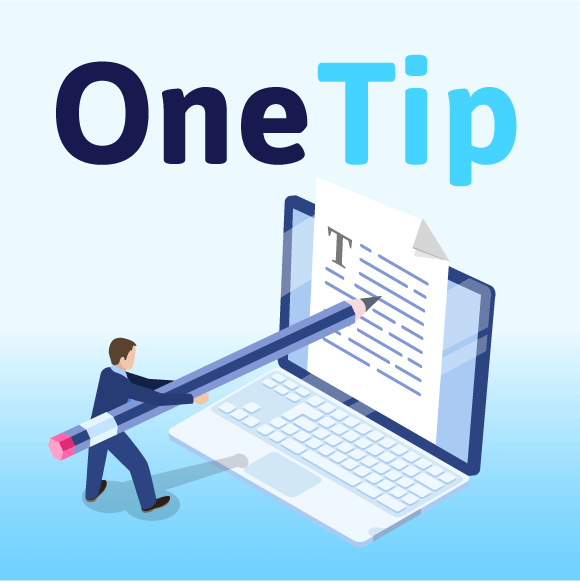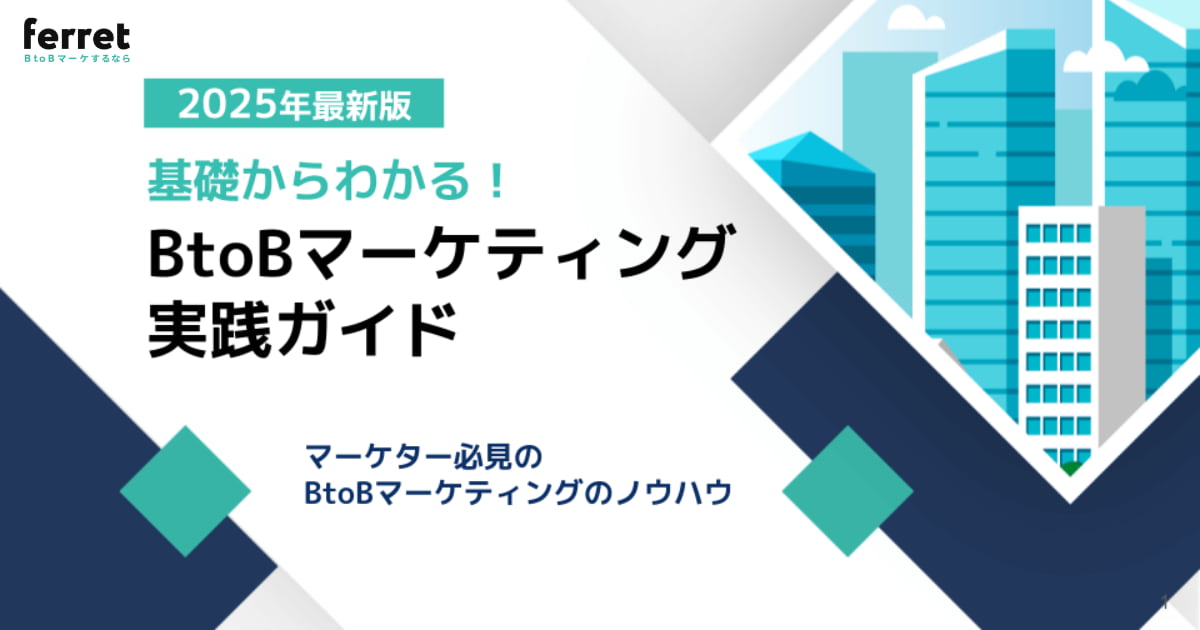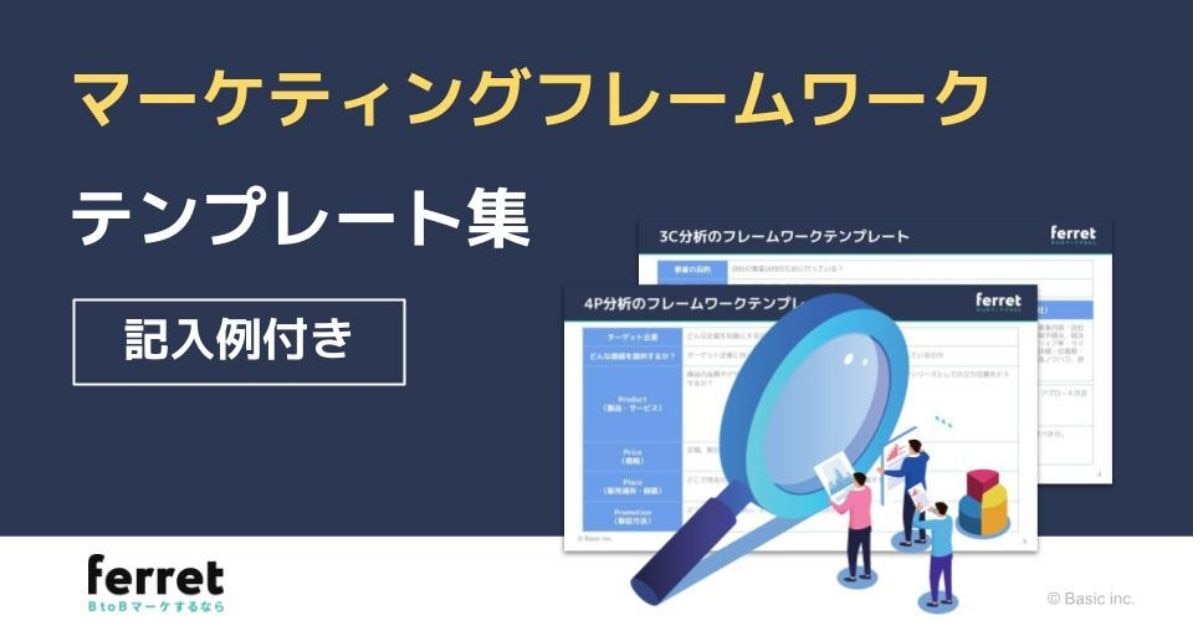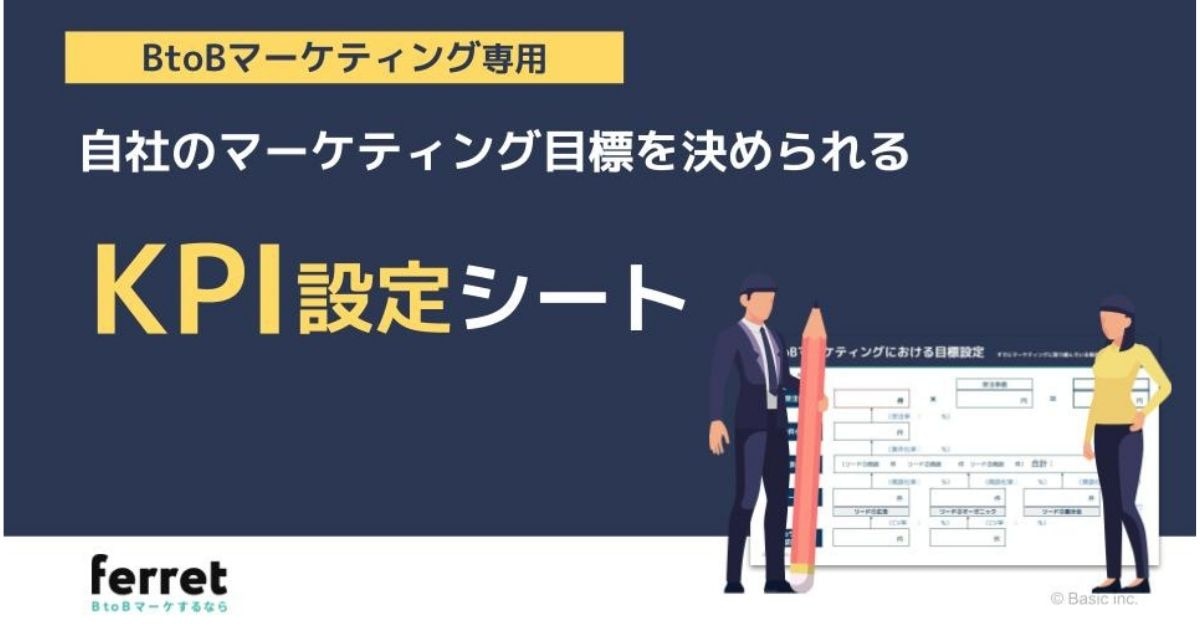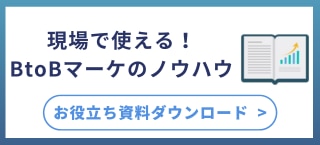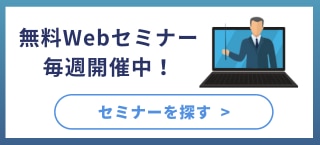オウンドメディアとは?基礎知識から立ち上げ・運用方法まで編集部がリアルに解説

オウンドメディアとは、自社で管理するメディアのことです。Webサイト(サービスサイト、コーポレートサイト、ECサイト、ブログ)やメールマガジン、パンフレットなどの紙媒体もオウンドメディアに含まれます。
最近ではWebサイト、特にブログを活用して、見込み顧客と接点を持ち、新規顧客獲得を行っている企業が増えており、注目のマーケティング手法といえます。そのため、マーケティング施策の文脈では「企業ブログ」を指して使われることも多い用語です。
この記事では、オウンドメディアで成果を出すために、オウンドメディアの基礎知識はもちろん、本ブログを運営して培ったノウハウをもとにした実践的な立ち上げ方・運用方法まで解説します。
オウンドメディアの立ち上げを考えている方、運用しているが成果が出ていないという方はぜひ参考にしてみてください!
■オウンドメディアの立ち上げからSEO記事制作代行までご支援します!気軽にご相談ください。
>ferretサービス紹介資料のダウンロード(無料)はこちら
目次[非表示]
オウンドメディアとは?

オウンドメディアとは、自社で管理するメディアのことです。Webサイト(サービスサイト、コーポレートサイト、ECサイト、ブログ)やメールマガジン、パンフレットなどの紙媒体もオウンドメディアに含まれます。
マーケティングの観点では、Webサイト、主にブログを活用し、潜在顧客からの認知を獲得からファン化・リード獲得までの役割を担っています。そのため、「オウンドメディア」=「企業ブログ」という意味で使われることも多いです。
オウンドメディアの目的とは?
オウンドメディアの最終目的は、企業のファンを作ったりリードを獲得したりして、商品・サービスの成約率を高めることです。
ただ、その最終目標の前のどこまでをオウンドメディアに担わせるかは事業の成長度合いによって異なります。例えば以下のようなものが考えられます。
- 認知度が低い商品・サービスの場合、認知度拡大
- 認知度はあるが競合が多く、購入する人が伸び悩んでいる場合、ブランディング・ファン化
- 採用応募者とのマッチングがうまくいっていない場合、リクルーティングの強化
さらに、企業ブログを活用する施策なら、SEOによる自然流入増加が見込めるため、広告に依存した集客体制の改善も見込めます。
つまり、企業によってオウンドメディアの目的は異なるのです。オウンドメディア立ち上げ時には、自社のオウンドメディアの目的を明確化する必要があることを念頭に置いておきましょう。
関連記事:オウンドメディアを運用する目的とは?目標・戦略設計のやり方
オウンドメディアが「意味ない」と言われる理由とは?
オウンドメディアを作成しても意味がないと言われる大きな要因は、すぐに成果が上がらないことにあります。オウンドメディア(企業ブログ)によるマーケティング施策はSEOが必須なため、年単位の中長期的な目線が必要です。
そのため、一定期間はリソースや予算を回収できない時期が続き、成果が見えないまま「意味ない」と感じてしまいます。
成果が上がらない理由としては、主に以下5つの要因が考えられます。
- 成果を早く求めてしまう
- 社内理解が不十分で非協力的
- 運営体制が整っていない
- オウンドメディアの運営目的が不明確
- SEOの知見が足りていない
オウンドメディアは、ターゲットユーザーとの接点を増やし、徐々に関係性を構築することで最終的な商品・サービスの成約につなげる施策です。時間的リソースが必要なことを前提に考え、社内全体で共有しておくのがおすすめです。
上記の内容に該当している場合は、まず該当理由を解消することから始めましょう。
■オウンドメディアの立ち上げからSEO記事制作代行までご支援します!気軽にご相談ください。
>ferretサービス紹介資料のダウンロード(無料)はこちら
オウンドメディアとWebサイト(ホームページ)の違い
広義の意味では、オウンドメディアとWebサイトは同じものです。オウンドメディアは「自社が管理しているメディア」を指すため、Webサイトも該当します。
マーケティング施策としてのオウンドメディア
ただし、マーケティング施策としてのオウンドメディアは役割が異なります。マーケティング施策においてのオウンドメディアはターゲットユーザーに対して有益なコンテンツを提供して、リードを獲得したり、最終的には商品・サービスを成約させる役割を担うWebサイトです。
そのため、マーケティング施策の文脈で「オウンドメディア」と呼ぶ際は、「企業ブログ」を意味することが多々あります。「Webサイト」と呼ぶ際には、「サービスサイト」や「コーポレートサイト」、「企業ブログ」などすべての総称として使います。
オウンドメディアはどこに立ち上げるのか?
オウンドメディアはサービスサイトやコーポレートサイトとは別に作成されるケースと、サービスサイトやコーポレートサイト内で立ち上げるケースがあります。
ターゲット・コンセプトが同じであれば、サービスサイトやコーポレートサイト内にコンテンツを作成しましょう。オウンドメディアで集客し、ホワイトペーパーやサービス紹介資料をダウンロードしてもらうリード獲得施策がやりやすくなります。
もしも、ターゲットやコンセプトが違う場合や管理を分けたい場合などは、別ドメインを取得してオウンドメディアを作成してもかまいません。
オウンドメディアとホームページの違い
「オウンドメディアとホームページはどう違うのですか?」という質問をよくいただきます。その違いを説明する前に、まずホームページとWebサイトの違いを理解しておきましょう。
Webサイトは、企業や個人が持つ複数のページで構成された全体の構造を指します。言い換えれば、Webサイトはコンテンツを集約した「場所」です。
一方で、ホームページは、そのWebサイトのトップページのことで、サイト全体の中心的な役割を果たします。つまり、Webサイトが「場所」であるなら、ホームページはその場所の「玄関口」と言えるでしょう。
ただし、日本では多くの人が「ホームページ」と「Webサイト」を混同して使われてしまっています。実際には、「ホームページ」という言葉が「Webサイト」と同義に使われることが多いのが現状です。
そのため、「オウンドメディアとホームページの違いは?」という質問に対しては、「オウンドメディアとWebサイトの違い」と同じ内容で答えることができます。
オウンドメディアを運用するメリット

企業がオウンドメディアを運用することのメリットを解説します。立ち上げ時に上層部から承認をもらう際の説得材料として説明する必要があることでしょう。必ず言語化して理解しておくのがおすすめです。
- 潜在顧客からの認知を獲得できる
- 信頼獲得できる
- リード獲得できる
- コンテンツが自社の資産になる
潜在顧客からの認知を獲得できる
オウンドメディアで公開した記事がGoogleなどの検索エンジンで上位表示されるようになると、悩みを持つ潜在顧客に対して情報を届けることができます。
自社にマッチする潜在顧客との接点を増やすためには、見込み顧客がどのような課題を抱えているのか、そしてその課題に対してどのようなキーワードで検索するのかを予測することが重要です。
これに基づき、SEO対策を施した記事を作成・更新していくことが、オウンドメディア運用の主な業務となります。
関連記事:【基本】SEOはキーワード選定が9割!すぐ実行できる手順とツール
信頼獲得できる
検索を通じてオウンドメディアの記事にたどり着いた潜在顧客が「疑問が解決した」「わかりやすい」と感じてくれることで、企業への信頼感が高まります。さらに、見込み顧客が抱える課題に対する解決策を網羅することで、「役立つ情報を提供してくれるメディア」として信頼を得て、ファン化を促すことができます。
信頼されるようになると、顧客は自発的にオウンドメディアを訪れるようになります。重要なのは、オウンドメディアを訪れた潜在顧客の期待に応え続けることです。
リード獲得できる
オウンドメディアで役立つ情報を発信するだけでは、潜在顧客が「なるほど」と思って離脱してしまうことがあります。しかし、「もっと詳しい情報が知りたい」「実践的な活用方法が知りたい」と思わせる次のステップを提供することで、リードを獲得することができます。
たとえば、オウンドメディアの記事で検索流入を獲得し、記事内でホワイトペーパーを提供する場合、そのホワイトペーパーをダウンロードするためにメールアドレスを入力してもらうことでリードを獲得できます。
■リード獲得施策の例
弊社では、各記事に関連するホワイトペーパーを設置。ノウハウを集めている読者に訴求することで、記事の流入をリードの獲得につなげています。
下記は、実際に「導入事例の書き方は? 効果とは? よくある10の疑問」という記事に設置している、ホワイトペーパーへの誘導例となります。
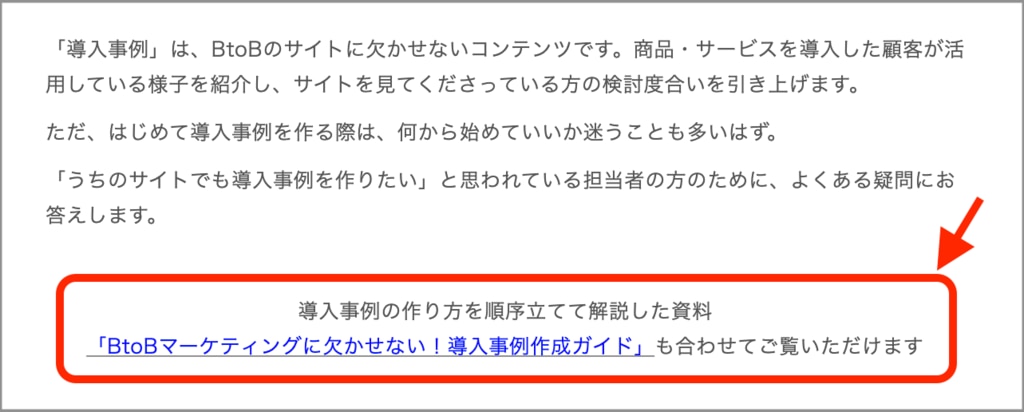
関連記事:リード獲得とは?見込み顧客を増やす方法一覧。始め方~ナーチャリング方法まで解説
コンテンツが自社の資産になる
オウンドメディアによって、自社が持つ潜在顧客に有益な情報を言語化することは有意義です。これまでも言語化できていなかったり、口頭だけで伝えていた潜在顧客に喜んでもらえるような
情報があったのではないでしょうか。
そのような情報の言語化を進め、潜在顧客にも伝わるように追求することそのものに意味があり、言語化したコンテンツは自社のかけがえない資産となります。
まず、作成したコンテンツが、継続した集客効果を発揮します。さらに潜在顧客向けに言語化したことで、今後のソーシャルメディアやセミナー、資料などのクオリティが上がることでしょう。将来的に書籍化できるほどの情報が蓄積するきっかけになるかもしれないのです。
トリプルメディアとは?オウンドメディアとの連携

企業が見込み顧客と接点を持つためのメディアには、「オウンドメディア」以外に「ペイドメディア」と「アーンドメディア」があります。この3つのメディアは総称して「トリプルメディア」と呼ばれています。
ペイドメディア、オウンドメディア、アーンドメディアそれぞれの特性をしっかりと理解し、効果的に組み合わせることで、企業は強力なマーケティング戦略を構築することが可能です。ここでは、各メディアの特徴や役割、具体例について解説します。
ペイドメディアとは?
ペイドメディアとは、広告を通じて有料で利用するメディアのことです。たとえば、テレビCM、新聞広告、インターネットのバナー広告、リスティング広告などがこれに該当します。
効果的な活用方法
ペイドメディアは、短期間で大規模なオーディエンスにリーチするために非常に効果的です。特に新商品の認知拡大や新サービスの市場浸透を早めたい場合に有効です。
メリット
ペイドメディアの大きなメリットは、ターゲティングが可能な点です。広告プラットフォームの進化により、地域、年齢、興味関心など、細かくターゲットを絞ることができるため、的確なオーディエンスにメッセージを届けることができます。
アーンドメディアとは?
アーンドメディアとは、企業が自発的に発信するのではなく、消費者や第三者によって生成されるメディアを指します。口コミ、レビュー、SNSでのシェアなどが主な例です。
効果的な活用方法
アーンドメディアは、企業がコントロールしない形で自然に広がるため、第三者の率直な意見として受け取られやすく、信頼性が高いのが特徴です。また、うまく「バズる」ことで製品やブランドの認知度を一気に高めることができます。
メリット
最大のメリットは、信頼性の高いユーザーの意見が広がることで、無償の広告効果を得られる点です。ただし、企業が直接管理できないため、悪評が広がるリスクも伴います。そのため、日常的なモニタリングや迅速な対応が必要です。
関連記事:BtoB向けSNSマーケティングの効果的な活用手順を徹底解説【事例付】
トリプルメディアの活用例
効果的なトリプルメディア戦略は、これら3つのメディアをバランスよく組み合わせることにあります。それぞれのメディアには独自のメリットがあるため、一つに偏らず活用することで相乗効果を得られます。
例えば、ペイドメディアで新商品の存在を広く知らせ、オウンドメディアで詳細情報や価値を伝えます。さらに、アーンドメディアを通じて顧客の口コミを引き出すことで、ブランドの信頼性や認知度を向上させるといったアプローチが考えられます。
成功するオウンドメディアの立ち上げ方
オウンドメディアを立ち上げるためには、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか。オウンドメディアを成功へ導くために、具体的な手順をご紹介します。

- 目的を明確にする
- ペルソナを定める
- テーマを定める
- KGI・KPIを設定する
- 実行計画を策定する
- キーワードを選定する
- 目標達成までの動線を設計する
1.目的を明確にする
オウンドメディアを運営することで何を狙うのか、目的を明確にしましょう。
資料のダウンロードでリード獲得を図ることでもよいでしょう。自社情報を発信することでブランディングに役立てようということも考えられます。自社の課題を認識し、課題解決にオウンドメディアを活用してください。
オウンドメディアの目的を明確に定めなければ、目標を定めることも、どのような運用が適切なのかも考えられません。
関連記事:オウンドメディアを運用する目的とは?目標・戦略設計のやり方
2.ペルソナを定める
ペルソナとは、オウンドメディアの典型的なユーザー像・人物像のことです。自社のターゲットユーザーのことでもあります。
どのような方にオウンドメディアに触れてほしいのかを考えましょう。年齢や性別、年収、住まい、家族構成、役職、趣味、特技、ライフスタイルなど、より具体的な情報を設定する必要があります。オウンドメディアの方向性が明確にするための重要な工程です。
BtoB・BtoCによってもペルソナで設定する観点が異なります。
関連記事:BtoBマーケティングのペルソナ設定とは?個人と組織の2つ作成するのがポイント
関連記事:ペルソナシートの作り方|情報収集や項目設定から丁寧に解説【無料テンプレート付き】
3.テーマを定める
どのような情報を発信するオウンドメディアなのか「テーマ」を決定しましょう。
設定したペルソナが知りたい内容がテーマになります。オウンドメディアがペルソナに、どんな気づきを与え、どんな行動を促すのか、どんな利益をもたらすのかを考えていくとテーマが決められるはずです。
テーマを決めると、発信する情報に目的意識が生まれ、一貫性を保つことができます。また、メディアの存在意義を社内で共有することで、社内でメディアへの愛着も高まりますし、運営のモチベーションも維持できます。
4.KGI・KPIを設定する
KGIはオウンドメディアのゴール、KPIはKGIを達成するための中間的な数値指標のことです。オウンドメディアの運用では、この数値と現在の差異を定期的にチェックし、運用をしていきます。
たとえば、オウンドメディアの「KGI」がリード獲得数の増加であるとします。その場合の「KPI」は潜在顧客を集めるためのユニークユーザ数の増加、自然検索流入の増加などに設定できます。
▼順番に数字をいれるだけでKPIが導き出せるワークシートもぜひご利用ください。
→BtoBマーケティング専用自社のマーケティング目標を決められるKPI設定ワークシート
関連記事:コンテンツマーケティングのKPI設定方法とは?効果的な運用方法も紹介
5.実行計画を策定する
オウンドメディアを運用するには手間がかかり、期間も長期にわたります。そのため、実行計画を策定して、無理のない運用を行うことが重要です。
具体的には、編集やライターの体制、内製か外注か、どれくらいのペースで記事を投稿し、ライティングはどれくらいのボリュームで行うのかなどを策定します。
無理な計画を立てると、継続できずに頓挫してしまうので、実現不可能な計画を立てないように注意してください。
6.キーワードを選定する
ユーザーの疑問は検索キーワードに現れます。その検索キーワードに合わせたコンテンツを作る必要があります。
どのようなコンテンツを作るかを決めるために、キーワードを選定しなくてはなりません。メディアが想定するターゲットが抱えていそうな悩みから、検索しそうなキーワードを企画しましょう。
キーワード選定においては、Googleが提供する「キーワードプランナー」などのツールを活用します。月間の検索ボリュームがどれくらいあるかを参考に、ターゲットユーザーが検索するキーワードを探しましょう。
キーワード選定に使えるワークシートをご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
関連記事:【基本】SEOはキーワード選定が9割!すぐ実行できる手順とツール
7.目標達成までの動線を設計する
オウンドメディアでは、記事を読んだ後にユーザーに取ってほしいアクションが何かを明確にしておきましょう。資料請求や問い合わせ、メルマガ登録、会員登録、ホワイトペーパーダウンロードなど、さまざまなものが考えられるはずです。
せっかくコンテンツを公開して一定のアクセスを獲得できたとしても、ユーザーに取ってほしいアクションを得られなくては成功とはいえません。
SEOに強い記事を書くためのテンプレートを配布しておりますので、ぜひご活用ください。
→迷わず、サクサク書ける!ブログ記事構成フォーマット
関連記事:【担当者解説】オウンドメディアのコンバージョン率改善方法を共有します
成功するオウンドメディアの運用方法

多くの流入を得て、さらにはリード獲得まで実現できる。そんな成功するオウンドメディアにするための運用方法をご紹介します。
当ブログOneTipを運営している実績に基づいた方法になります。ぜひ参考にしてみてください。
- 長期的に運用する前提で立ち上げる
- ユーザーファーストを徹底する
- 競合に負けない魅力的なコンテンツを作る
- 記事はリライトが必須
- 他の施策と連携して、相乗効果を引き出す戦略を取りいれる
- コンテンツを拡散する仕組みを作る
長期的に運用する前提で立ち上げる
オウンドメディアは長期施策です。運営には手間や時間がかかります。
そのため、成果が出ないことで上層部からの理解が得られず運用がストップしてしまう企業が数多く存在します。その大きな原因は立ち上げ時の準備不足です。
重要なことは「いつまでに、どのくらい成果を出すのか」という具体的な計画を立てて、上層部への理解を得た上でオウンドメディアの運用を始めることです。
成果が出る前の準備段階で運用が停滞しないように、長期的な視点で運用を始めましょう。
ユーザーファーストを徹底する
オウンドメディアの運用では、何よりもユーザーファーストを徹底することを忘れてはいけません。その理由は主に2つです。
- 何度も訪問してもらう
- SEO施策
オウンドメディアは、コンテンツの内容や画面設計などユーザー満足を第一に考えて作ることが重要です。ユーザーの知りたい情報やユーザーが使い勝手のよいサイトにすることで、何度も訪問してもらえ、それによってメディアで成果を出すことができます。
また、ユーザーファーストであることはSEOにおいても重要です。検索順位を決めるGoogleのアルゴリズムでも最も重要とされているため、結果的に順位上昇・流入増加につながる要素にもなります。
ユーザーファーストを徹底するには、ユーザーのニーズを深く理解し、彼らが抱える課題や疑問に的確に応えるコンテンツを提供することが重要です。
関連記事:【基本】Googleアルゴリズムとは?10年経っても変わらない原理
競合に負けない魅力的なコンテンツを作る
オウンドメディアを運用する際、すでにあるようなコンテンツを発信しても意味がありません。SEOの観点からみても、検索上位に入ることが難しく、そもそも見てもらえません。
したがって、オウンドメディアを効果的に運営するためには、競合メディアの分析が欠かせません。競合がどのようなコンテンツを作成しているのか、どのキーワードでSEO対策をしているのかを調査し、自社との差別化ポイントを見つけることが成功への鍵となります。
まず記事を作る際は、競合分析ツール(例えば、SimilarWebやAhrefsなど)を活用して、同じ検索キーワードで記事を作成している競合サイトをチェックしてみましょう。「どうすればより魅力的な記事になれるか」という目線で、記事の骨子を検討し、内容を詰めていきます。
「より魅力的」にする要素を見つける方法は、「読者が競合メディアではなく自社のオウンドメディアを読む価値はどこにあるのか」を考えることです。例えば、よく言われるのは自社にしかもっていない情報「一次情報」を多く入れることです。競合が提供していない視点からの分析や、ユーザーの体験談を取り入れるなど、差別化できるポイントを見つけた際には、それを徹底的に掘り下げてコンテンツに反映させましょう。
関連記事:オウンドメディアの記事の書き方とは?編集部で共有しているライティングのコツ
関連記事:競合サイト分析とは?見つけ方やチェック項目、役立つフレームワークを解説
記事はリライトが必須
記事をアップして終わりではありません。記事を公開した後は定期的に順位の計測を行いましょう。オウンドメディアでキーワードを網羅できるようになってきたら、流入を安定させるためのリライトが運営の中心業務になってきます。
順位が思うように上がらない、または下がってしまう場合はリライトを行い、検索順位の維持・上昇させることが不可欠です。また、情報が最新であることによりユーザーからの信頼を保ち続けられます。
SEOに強い記事を書くためのテンプレートを配布しておりますので、ぜひご活用ください。
→迷わず、サクサク書ける!ブログ記事構成フォーマット
他の施策と連携して、相乗効果を引き出す戦略を取りいれる
オウンドメディアは他の施策と連携することで相乗効果を生み出します。例えば、以下のような施策です。
- SNS:コンテンツが広く拡散されれば、流入が増加する
- メール:メルマガでお役立ち記事を送れば、ファン化や検討度の向上を促せる
- SEO:検索順位上位を獲得できれば、流入が増加する
目的によって、連携すべき施策は変わってきますので、連携して何を達成したいのかを考えて運用しましょう。
コンテンツを拡散する仕組みを作る
公開したコンテンツは、ユーザーに拡散してもらうことで、これまでなら接点のなかった人たちにも情報を届けられるようになります。
そのためにも、企業のSNSアカウントのフォロワーを増やしたり、社員それぞれがSNSを運用したりすることが重要です。
■コンテンツ拡散例
弊社の運営しているBtoBマーケティングのメディア「One Tip」では、記事を公開したあとに社内メンバーでSNSによる投稿・シェアを行っています。
下記は、社内メンバーのツイートを元に社外の人々にもシェアをいただき、SNS経由で多くの流入を獲得した記事例となります。
オウンドメディアの成功事例4選
オウンドメディアのメリットを十分に活かし、成功しているオウンドメディアは数多く存在します。その中でも、顕著な事例を4つ紹介しましょう。
ベーシック:BtoBマーケ支援会社のノウハウを自社メディアでも実践
弊社株式会社ベーシックが運営する本ブログ「One Tip」もBtoBマーケティングの実践情報を発信するBtoB向けオウンドメディアです。
オウンドメディア強化のために、潜在顧客向けのキーワードにも注力して公開記事数を増加させたり、CVやリンクの導線設計を見直すなど、オウンドメディア強化を行いました。その結果、1年でオウンドメディアセッション数252.9%増加、リード獲得数175.6%増加などの成果をあげることができました。
関連記事:【成功事例11選】BtoBのオウンドメディアでリード獲得するには?
「SmartHR」:網羅性と専門性を両立
メディアURL:https://mag.smarthr.jp/
SmartHRは労務管理クラウドソフトです。「SmartHR Mag.」と「SmartHR ガイド」の2つのオウンドメディアを展開しています。とくにSmartHR Mag.は、2019年3月には前期同月比3.9倍の成長をし、検索上位を多数獲得しました。
記事のテーマにおいて選択と集中を行ったことで、網羅性と専門性のあるメディアを作ることに成功しています。たとえば、2019年4月に働き方改革法が施行されたため、その時期に集中して労務管理関連記事を公開していました。
「キーエンス」:高品質な資料でリード獲得
メディアURL:https://www.keyence.co.jp/solution/
キーエンスは東証一部上場の大手企業で、センサや画像処理機器など主に製造メーカー向けの製品を提供する企業です。自社の提供製品にかかわる技術資料をふんだんに掲載した辞書型のオウンドメディアを複数運営しています。
魅力的な資料をダウンロードするには会員登録が必要で、会員登録により多くのリードを獲得していることがうかがえます。
ダウンロードして数時間後には、営業部が状況ヒアリングと製品説明の電話を実施。日程が合えば、1週間後には営業担当者が製品サンプルを持って企業にデモや説明に行くスタイルを取っています。技術力に自信がある企業であれば、ぜひ参考にしたいオウンドメディアのスタイルです。
「サイボウズ」:インタビュー記事でノウハウを発信
メディアURL:https://cybozushiki.cybozu.co.jp/
サイボウズはソフトウェアの開発と提供を行う会社です。サイボウズが運営するオウンドメディア「サイボウズ式」は、業務効率化を図るためのお役立ち記事に加えて、働き方や会社組織についての発信も行っています。サイボウズがどのような企業なのかなどの考え方や思想も見えるコンテンツもあり、採用強化にもつなげられる内容です。
著名人へのインタビュー記事も多く、読みやすい工夫がしてあるため、多くのビジネスマンに支持されているオウンドメディアです。
BtoBマーケティングならferretにご相談ください

弊社の提供するferretは、BtoBマーケティングに特化した支援サービスです。BtoBマーケティングに必要な機能が全て揃ったマーケティングツールとコンサル・代行支援を提供しています。
以下は、サービスの一例です
- BtoBマーケコンサルティング:キーワード調査や競合調査などを通して情報を整理し、確実に成果を出すための計画を作っていきます。
- SEO記事制作代行:ターゲット顧客像の整理・キーワード調査から、ライティング・校閲まで一貫したご支援で質の高い記事を制作いたします。
マーケティングにお困りごとがある方はぜひご相談ください!
>ferretサービス紹介資料のダウンロード(無料)はこちら
オウンドメディアでマーケティングを加速しよう
オウンドメディアは、潜在ユーザーから顕在ユーザーまで幅広いユーザーにアプローチできる手法です。成果を出すまでに時間はかかりますが、将来に大きな成果を出すことができるといえます。
ただ、実際にオウンドメディアを始めようとすれば、以下のような課題に直面することがあります。
- 自社内でのリソースが不足している
- 運用するときに必要な手順がわからない
オウンドメディアの構築・運用にあたって上記のような不安があるなら、弊社のサービス「ferret」をご検討ください。
「ferret」は、マーケティングツールの提供からコンサル・運用代行まで、貴社に最適な施策をご提案します。
SEO記事制作代行では、ターゲット設定やキーワード調査、ライティング・校閲までを一貫対応し、成果につながる記事を制作。
マーケティングにお悩みの方は、ぜひ資料をご覧ください!